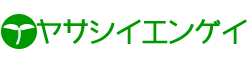一度見たら忘れられないユニークな花。性質は案外強い。
オダマキ
 |
科名:キンポウゲ科学名:Aquilegia flabellata原産地:北半球総種数:約50種草丈:30cm-80cm主な開花期:5月-8月栽培難易度
|
由来・来歴
日本が原産のミヤマオダマキと、ヨーロッパなどが原産の西洋オダマキの2グループに大別されます。ミヤマオダマキは白から紫までの色幅があり、変わったところでピンクがかった園芸品種もあります。草丈は20-30cmで、径4cmほどの花をつけます。それに対して西洋オダマキは、草丈70cmに達し、花色も、赤・桃・白・黄などカラフルです。花はおおよそ5月〜6月頃の初夏に咲きます。
由来・来歴
オダマキの名前は、中心を空洞にして巻いた麻の糸玉「苧環」に花の形が似ているところから付けられました。花が開いた形と言うより、つぼみの形が苧環に近いと思います。
学名のAquilegia(読み方はアクイレギア、アクレギアなど)の由来には諸説があります。
・アクア+レギア ラテン語で水を表す「アクア」と集めるという言う意味の「レギア」の2語から来ており、花びらが筒状で漏斗(じょうご)のような形になっているところから。
・アクィーラ ラテン語で鷲を表す「アクィーラ」から。花の距(きょ)の部分がくちばしのようにみえるところに由来。※距については後述の姿・形の項を参照
姿・形
花は5枚の萼(がく)と筒状の花びらからなっており、がくの後ろ側には距(きょ)が角のように突き出ています。葉っぱは長い軸の先に3枚の小さな葉が付いた三出複葉(さんしゅつふくよう)です。花後、花茎の先に細長い莢が5つ集まった果実を付け、熟すと先端が開いて中から光沢のある黒いタネが出て来ます。
 花の構造 |
 葉っぱ |
 花後の果実 |
仲間
( )内は学名。A.はAquilegia(アクレイギア)の略
・オダマキ(A. flabellata) ミヤマオダマキを園芸化したもので、日本では単にオダマキというとこの種を指すことが多いようです。それ以外のものはセイヨウ〜やミヤマ〜のように頭になにか付きます。草丈は30〜50cm、花色は青紫から白まで幅があります。
・ミヤマオダマキ(A. flabellata var.pumila) 日本の高山地帯に分布するオダマキの野生型です。草丈は20cmほどです。花色は青紫色で花びら(がく片)から白まで色幅があります。暑さにやや弱い。「ミヤマ」は漢字で書くと「深山」です。
・セイヨウオダマキ(A. vulgaris) ヨーロッパからシベリアにかけて広く分布します。花色は紫色でうつむきかげんに咲きます。草丈は50cm〜60cm、日本での開花は主に5月〜6月。他の種との雑種が多く、人の手によって改良された様々な園芸品種があります。赤、ピンク、白などの花を咲かせるもの、大輪種や八重咲き種などバラエティーに富んでいます。
・カナダオダマキ(A. canadensis) カナダ、アメリカのテキサス州に分布します。花びら(がく片)はあまり大きく開きません。
その他画像
 セイヨウオダマキ オリガミミックス |
 セイヨウオダマキ オリガミミックス |
 チシマルリオダマキ |
 カナダオダマキ |